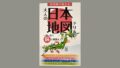はい、先月の一ヶ月チャレンジで始めた小学生からの算数学び直しが継続中の妹です。
ようやく分数やら、公約数やらの勉強が終わり、二次元の面積を求める勉強が始まった。算数なのでまずは簡単な正方形や長方形、それから三角形や台形などに移行する。それぞれの面積を求めるには公式があり、それを覚えていくのだが混乱しまくっている。
扇形でつまづく
台形まではなんとかなった。そして円も辛うじてどうにかなった。だが扇形。こいつはとんでもなく厄介な図形だった。なにせ面積や弧の長さを出すのに、円周率の小数の計算と角度によって変わる分数の計算が加わる。
それらを当然頭から順に解いているようじゃダメだ。そんなことをしていたら時間がかかる。分配法則や結合法則を用いて、計算を楽にする工夫が必要なのだ。
つまり、ただでさえ計算が複雑になっている上に、計算を簡略化するための気付きが必要ということになる。同時にそのどちらもこなすなんて、小学生はすごいなと改めて感心した。
複雑怪奇な図形の面積
どうしたらそんな意地悪な面積を求めろという風になるのか、とんでもない図形の面積を今まで学んだ全ての知識を活用して求めさせられる。
台形の中に扇形が入っていて、さらにそれが分かれていたりする。こっちの図形とこっちの図形を組み合わせたら、半円になるからその面積を割り出して、大外の台形の面積から引いて求める。そしてこの間にある、なんだかよく分からない三角形の面積まで求めさせられる。みたいな調子だ。
もうそんなごちゃごちゃした面積を求めなくてもいいのではないか?と、ついつい苦手意識が顔を出す。結局どこかで理解が浅いから、複雑になると太刀打ちができない。
もう一度どこがよく分かっていないのか、時間をかけて解きほぐさないと、やっぱり同じところでつまづくだろう。
進んでは戻るの繰り返し
そんなわけで再び小数や分数の計算をドリルでやっている状態。しかも未だに時々間違えるのだから、やっぱりうかつというか記憶に定着していない。整数×分数の場合は分子にかける、整数÷分数の場合は分母にかける。そんな基本的なことさえうろ覚えでよく間違える。
さらに小数の計算では未だに小数点の位置を平気で間違えたりする。いやいや、こんな調子で大丈夫なのか?と自分でも呆れるが、算数は何度もやる以外近道はない。勉強し直してそれはよく分かっている。なのでひたすら間違えなくなるまでやり続けるしかない。
最近九九だけでは計算が追いつかない気がして、二桁の掛け算も暗記したほうがいいのではないかと思い始めている。以前買ったまま放置していた、インド式計算ドリルを今度やってみようかと思った。